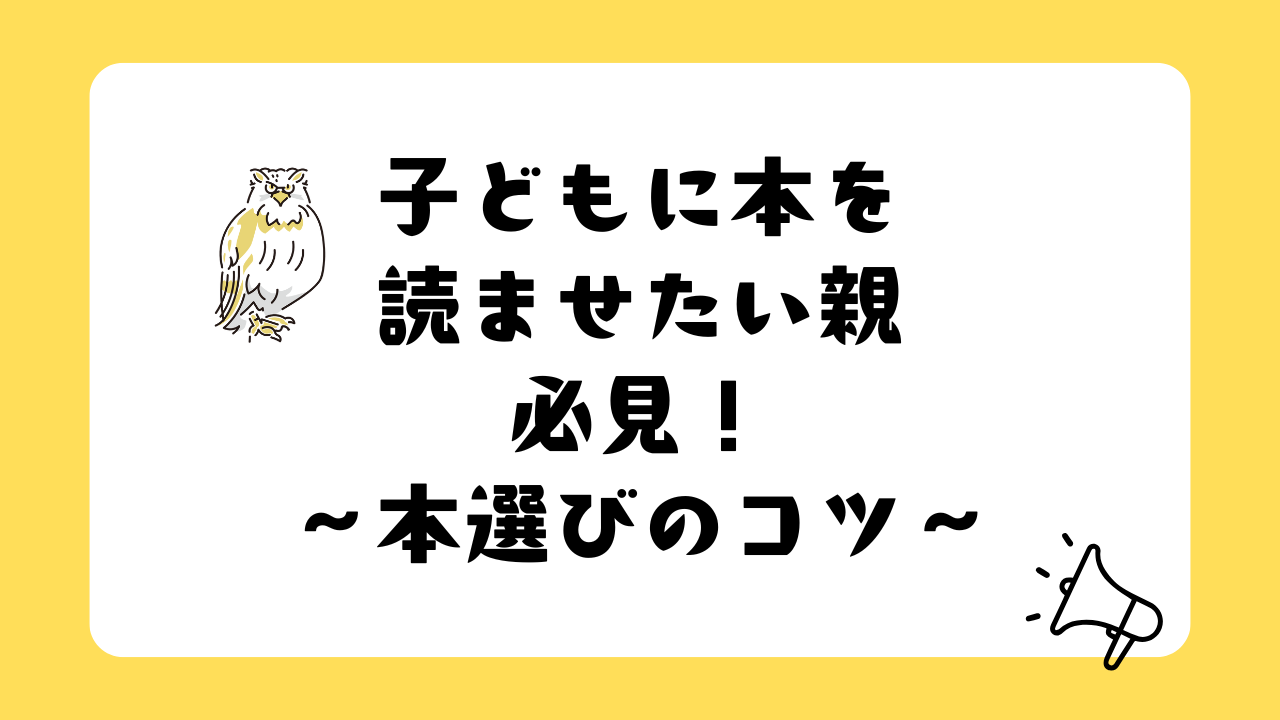「子どもに本を好きになってほしい。」―― 多くの保護者が願うことですが、実際には「なかなか本を読んでくれない」「うちの子はゲームばっかり」と悩む声をよく耳にします。ゲームやスマホのように放っておいても読書をしてくれればいいのですが、なかなかそういうわけにはいきません。読書が習慣になり、生活の一部になるためには、日々の工夫と努力が欠かせません。
本記事では、10年以上にわたり蓄積してきた経験に基づき、子どもが本を読みたくなるように仕向ける「本選びのコツ」をまとめました。
目次
親目線の本選び
大人が本を選ぶプロセス
私もそうですが、大人が本を選ぶ際にはある程度プロセスがあります。
まずは本を読む「目的」があります。「スキルアップしたい」、「〇〇の分野のことが知りたい」など、本を読む「理由」があります。そして、読みたい本の「分野」や「ジャンル」が決まっていたりします。そういう情報をもとに、書店に行ったり、図書館に行ったり、ネットで検索して本を探していきます。
そして、この本選びの方法は、子どもの本を選ぶ際にも適用されます。
子どもに本を読ませたい「目的」があります。読ませたい「分野」や「ジャンル」の本があります。ネットで検索する場合は「小学生 おすすめ 本」などと入力すれば、年齢やジャンル、テーマに合わせていろんな本を紹介してくれるサイトがたくさんあります。そんないろいろな情報を参考にしながら、子どもに読ませたい本を選んでいきます。
親が選んだ本を読んでくれない!
しかし、ここで問題が発生します。がんばって本を見つけてきたのに、子どもたちが読んでくれないのです。そう、我が家でもよく起こっていました。いくら時間をかけて本を探しても、いくら高いお金を払って買っても、肝心の子どもたちが読んでくれなければ意味がありません(泣)。
しかし、ここですぐに挫折してはいけません。もちろん色んな理由があるとは思いますが、親が選んだ本を読んでくれないのは、根本的に「親が読ませたい本」と「子どもが読みたい本」にギャップがあるからです。
親が子どもの本選びに失敗する理由
①読書を「勉強」と考える
多くの親が「本を読ませたい」と思うあまり、学習効果や知識の習得を重視してしまいがちです。けれど、子どもにとって読書はまず「楽しい」ことが大切です。「勉強のため」「国語の力をつけるため」などと位置づけられてしまうと、途端にハードルが高くなり、読書を避けるようになります。
②押しつけられると読みたくなくなる
「勉強しなさい」と言われると勉強したくなくなります。同じように、本を読ませようと親が頑張ると、子どもはかえって拒否反応を示します。子どもはとても敏感で、「本を読ませたがっているな」とすぐに感づくとすぐに読みたくなくなってしまうのです。
③子どものレベルに合っていない
私がよく経験したことでもありますが、子どもに読書をさせたいと考える親は「この本も」「あの本も」と欲張りになり、子どものレベルより難しい本を選びがちです。そうすると、子どもは「読みにくい」「つまらない」と感じてしまい、読書が続かなくなります。
④親が選ぶ本はおもしろくないという先入観
こういうことが度重なると、親が選んで来る本はおもしろくないという先入観が生まれます。そうなると、いくらおもしろそうな本を勧めても見向きもしてくれません。その本は本棚で埃がかぶっていき、本を読ませようと躍起になった親はイライラし始め、親子関係が悪くなっていくという悪循環に陥ってしまいます(実話)。
子ども目線の本選び
子どもには本の情報がない
大人には本を選ぶプロセスがあることをお話ししましたが、子どもの場合、特に幼児や低学年の間は本に関する情報がありません。最近どういう本が流行っていて、どういう本が人気があるのかなんて知りません。どんな分野があり、どんな本があるのかも知りません。ただ書店や図書館の児童コーナーに連れられて行くと、本がズラーっと並んでいて、そこから目についたものを選んでいくのです。
では、子どもたちはどうやって本を選んでいるのでしょうか。
本は第一印象で決まる
人の第一印象は、出会ってからわずか数秒、場合によっては0.1秒という非常に短い時間で形成されると言われています。これは本にも当てはまります。我が家の場合、「この本はどう?」と表紙を向けて差し出すと、子どもは「う~ん、、」と数秒で、「読む」「読まない」が決まります。
気になって、子どもに「読む」「読まない」を決める基準を質問したことがあります。

その基準って何なの?

いや、なんとなく。
子どもの「なんとなく」にはものすごく多くの意味が含まれます。表紙を見ただけですが、そこから多くの情報を直感的・感覚的に読み取り、「タイトルがおもしろい」「絵がかっこいい」「イラストが多い」などというそれらしき理由が合わさり、「なんとなくおもしろそう」となって本を手にするのです。
子どもの好みを把握しよう
まずは子どもの興味を把握しましょう。もちろんこれはどこの親でもやっていることですが、興味のある分野やジャンルだけでなく、もっと細かい部分も観察してみましょう。
どういうイラストが好きなのか、どういうタイトルやテーマに興味を示すのか、彼らが本を選んでいる基準を見てみましょう。子どもの好みはコロコロと変わります。その日の気分で変わる場合もあるし、年齢によっては、挿絵が多いかどうかで選んでいる場合もあります。常にアンテナを立てて、子どもをしっかり観察し、それに合わせて本を紹介してあげるのがポイントです。
焦りは禁物
焦りは禁物です。親が焦っても子どもはついて来てくれません。親が頑張れば頑張るほど、子どもはやる気をなくします。私が考える親の役割は、子どもの興味を「サポート」し、「拡張」させてあげることです。子どもの読書をリードしようと考えず、焦らず、親の願いはグッと我慢し、サポート役に回りましょう。本を読む子を育てるのは長い旅です。だからこそ気長に、気楽に、もっと肩の力を抜いてやっていきましょう。
まとめ
まずは子どもに本を楽しんでもらうことが第一です。だからこそ、本選びにおいて最も大切なのは「子どもの視点」です。そのためには、まずは親の欲を抑えなければなりません。親目線で選ぶのではなく、まずは子どもの視点で本を選んでみましょう。親が勧めてくれた本がおもしろかったという経験が積み重なれば、親が選ぶ本にも信頼感が生まれ、読んでくれる確立も高くなるでしょう。